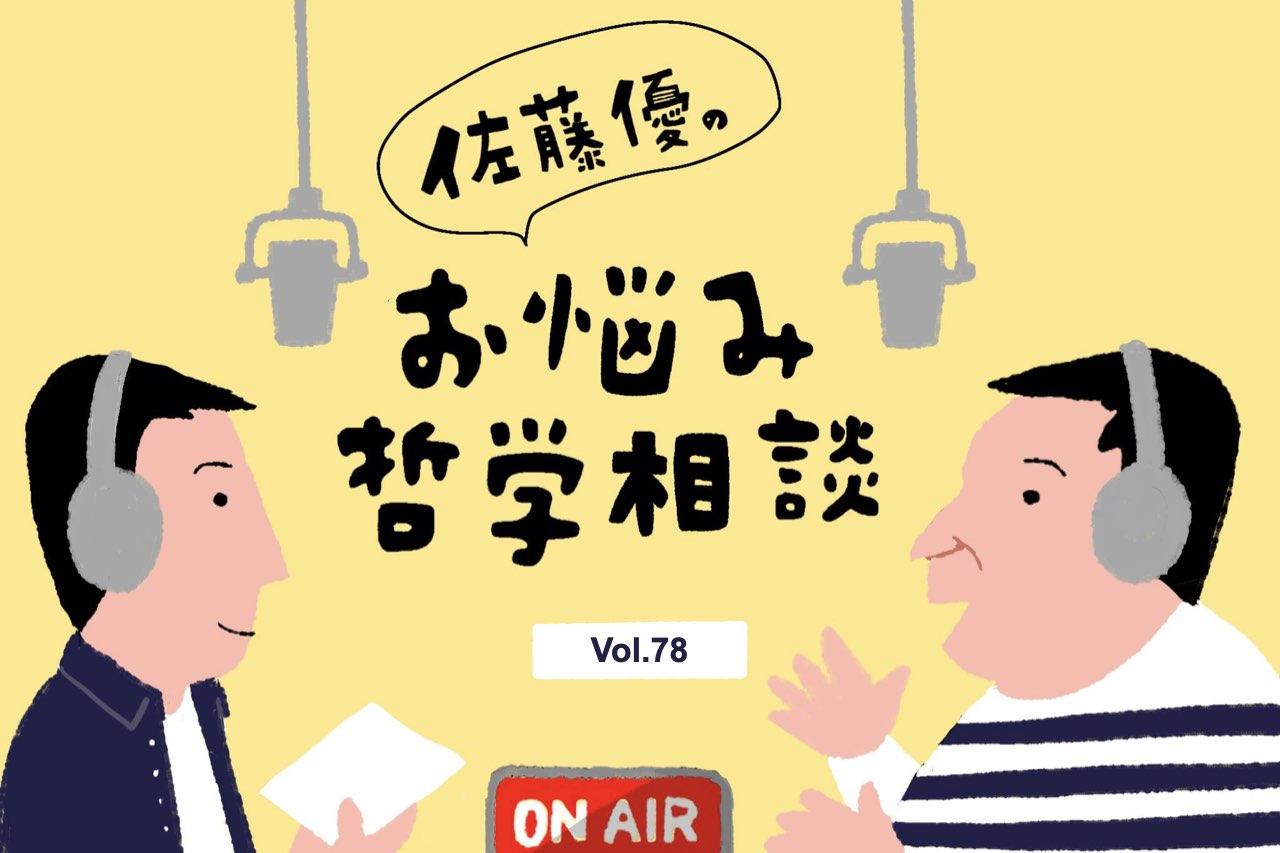
イラスト:iziz
シマオ:皆さん、こんにちは! 「佐藤優のお悩み哲学相談」のお時間がやってまいりました。読者の方にこちらの応募フォームからお寄せいただいたお悩みについて、佐藤優さんに答えていただきます。さっそくお便りを読んでいきましょう。
40代の医師です。私はしばしば職場などでトラブル解決の相談役を務めているのですが、当事者双方の理解と合意を導くことが困難な対立に遭遇することがあります。
佐藤さんは長年、外交上の根深い問題に取り組み、対話を通じて解決策を見出す努力をされてきました。
このような難しい場面での哲学実践において、特に心がけていることや、対立を乗り越えるために重要視しているポイントは何でしょうか?
(しもん、40代後半、男性、医師)
大学病院の出世争いが激しいわけ
シマオ:しもんさん、お便りありがとうございます。職場のトラブル解決で相談役を務められているとのことですが、医療の現場って一体どういうトラブルが起きるんですかね?
佐藤さん:文脈からすると、恐らく医師同士のトラブルではないかと思います。こういう医師間の対立というと、思い当たる小説はありませんか?
シマオ:あ、ついこの前の女性医師の方からの相談で推薦図書に上げていた山崎豊子さんの『白い巨塔』ですね!
佐藤さん:その通りです。恐らくですが、しもんさんもそのような環境で働かれているのではないかと。前にもお話ししたと思いますが、大学病院の医局におけるポストというのは、他の学部と違って非常に限られているんです。
シマオ:それぞれの医局に教授は基本的に1人だけ、でしたね。
佐藤さん:そうです。さらに各部長も1人、病院長も1人です。ポストがこのように限られている上に、誰もが超高学歴。その割には大学病院の医師の給料は高くはない。ですから誰もが必死で上を目指すわけです。ポストを巡る戦いは熾烈なものになります。
シマオ:た、確かにすごそうな世界ですね……。
佐藤さん:そういう組織では対立やトラブルが当たり前なんです。もちろん派閥もありますから、常にいろいろな場面でぶつかることになるわけです。
シマオ:『白い巨塔』では教授になるために主人公は必死になりますが、教授戦の際はもとより、普段からそういうことがあちこちであるわけですね。
佐藤さん:その通りです。ちなみに教授戦に敗れた方はどうなるかというと、本人はもちろんですがその派閥に属していた人間は、全員粛清されることもあります。
シマオ:粛清って! 怖いですね! 一体何が起きるんですか?
佐藤さん:全員が違う病院に飛ばされ、新しい教授の元で組織全体が刷新されます。
シマオ:ひえー!!
仲介や相談はむしろマイナスに働くことも
シマオ:改めて、大学病院がすごい競争社会であることは分かりました……。しもんさんが大学病院の方かどうかは定かではありませんが、仮にそうならば医局内の対立、医師同士のトラブルは不可避だということでしょうか?
佐藤さん:そういうことです。しかもそれが結局限られたポストを巡る争い、人事に結び付いていますから、対立もトラブルも自然なものだと受け入れるべきです。
シマオ:じ、じゃあ仲裁に入ったり相談役を務めたりすることは無意味なんでしょうか⁉
佐藤さん:対立を一時的に弱めることはできても、なくすことはできないと認識する方がよいでしょう。
大学病院などのポスト争いが根っこにある対立に関しては、最終的に勝ち負けをつけるしか解決策はないのです。つまりこの対立は大学病院、医局という組織の持つ構造的な問題だということです。
シマオ:ということは、むしろ下手に相談役など買って出ない方がいいとも言える……?
佐藤さん:そういうことだと思います。場合によっては、「あいつはどちらにもいい顔をしてコウモリみたいな奴だ。信用できない人物だ」と、双方からスポイルされかねません。
シマオ:それこそ損な役回りになっちゃいますね……。しもんさんのような立場だったら、どう対処するのが一番いいのでしょうか?
佐藤さん:強いて言うなら、とにかく対立する者同士の接点を極力少なくすることです。
両者の関係を良くしようとして交流の場を無理に設けたとしても、さらに火種や摩擦を増やすだけになってしまう可能性があります。お互い大人ですから、それぞれの仕事が特に大きな問題なく、上手く回ることだけに専念することです。
シマオ:なるほど、下手に対立を解消しようとか、理解させようということではなく、それぞれが一番問題なく動くことができる場を整える。そんなイメージでしょうか?
佐藤さん:そういうことだと思います。双方の会話もせいぜい天気の話くらいにとどめさせ、それ以上互いに入り込まない。一定の距離感をあえて作るということがポイントだと思います。
「事実・認識・評価」は分けて考えよ
シマオ:でも、対立の中にはどうしても調整が必要になる場合もあるかと思うんですよ。例えば、高額な医療機器が、ある派閥にとっては必要だけど、ある派閥にとっては不要、みたいなケースってあるんじゃないかと。
佐藤さん:確かにそういうケースはあるでしょうね。こういう問題が起きたときの対処法で、いつも私が言うのは「事実・認識・評価」を明確にするということです。
シマオ:確か前にもお話しされていましたね。 まず出来事や対象の客観的な「事実」をしっかり把握する、でしたよね?
佐藤さん:そうです。その上で、その事実をどのように「認識」するか? 立場やスタンスによって認識の仕方は異なってきます。
最後に出来事を「評価」するわけです。それがいいことであるか、悪いことなのか? あるいは望ましいことなのか、望ましくないことなのか?
対立している両者の「事実・認識・評価」がどうなっているかをまずは明確に把握する。その上で両者のどこが違っているのか? それを正すことで誤解が解けたり、対立的な関係が薄まったりすることがあります。
シマオ:なるほど。つまり、互いのズレがどこにあるか分からないからこそ対立しているケースもあるわけですね?
佐藤さん:その通りです。先ほどシマオくんが挙げた例であれば、まず導入機材が何なのか、その「事実」を両派閥ともにしっかり把握できていなければなりません。ですが多くのトラブルはそんな基本的な事実さえ間違っていることがあるのです。
シマオ:そもそも、導入する機材を勘違いしている、みたいなことですね。
佐藤さん:はい。次に、事実はちゃんと踏まえているけれどそれに対する認識が違っている場合。導入する機材がどれかは分かっているものの、その機材がどういう効果や働き方をするのか、認識がズレていたら当然ですが話は嚙み合いません。
そして仮にその認識が合っていたとしても、その機材を導入することで組織にどんな影響が出るか?プラスかマイナスか? その評価が違っていたらやはり対立になるわけです。
シマオ:なるほど。「事実・認識・評価」のどの段階で食い違いがあって対立しているのかを、まずははっきりさせるということですね!
理想や善意を抱かないことがポイント
佐藤さん:多くはそれが明確になった時点で解決への道が分かってきます。ただし、その上でさらに対立が続くようなら、いくつかやり方があるかと思います。
シマオ:教えてください!
佐藤さん:一つは上位概念を提示して説得する方法です。その機材は一見すると限定された医師だけが恩恵を受けるように見えるけれど、それによって病院経営自体が実は強化される。その結果、他の立場の医師たちにとってもプラスになると説得する。
シマオ:なるほど、視点を上にズラすことで、問題を派閥間の争いとは分けてしまうやり方ですね。
佐藤さん:そうですね。哲学的に言うのであれば弁証法的な解決法と言えるかもしれません。正(テーゼ)ー反(アンチテーゼ)ー合(ジンテーゼ)というものです。互いに対立するものも、より高い次元においては対立を乗り超えることができるということです。
シマオ:「アプローチは違うけど、向かう先は同じだよね」ってことですね。
佐藤さん:そうです。あるいは交換条件的な説得の仕方もあり得るでしょう。今回は確かに向こうの派閥にとって有用な機材を導入するけれど、順番で次は自分たちの派閥の希望を受け入れてもらう、というものです。
シマオ:これはすごく現実的で、実際によくある話ですね。
佐藤さん:いずれにしてもその根本にあるのはいたずらに互いを理解させようとか、仲良くさせようという善意や理想を描かないということです。
シマオ:むしろそのほうがうまくいく?
佐藤さん:はい。大学病院の医局という特殊な環境であればこそ、そのことを徹底することだと思います。なぜなら対立は構造的であって、その対立が結局病院経営の刷新や健全化にもつながる。それを誰もが理解した上での一種のゲームになっているからです。
会社では白黒つけないことが重要

イラスト:iziz
シマオ:ふ〜む、どうしても必要という時に調整は必要だけど、それ以外では勝ち負けがつくまで戦うしかないってことなんですね。調整の手法自体は僕みたいなビジネスパーソンにも生きそうだなとは思いましたが、白黒つけるっていうのは会社だと合わない気がしました。
佐藤さん:その通りだと思いますよ。一般企業において、大学病院の医師のような徹底して勝ち負けを決め、その上で粛清人事をやったらどうなると思いますか?
シマオ:もう想像しただけで悲惨なことになりそうな……。
佐藤さん:そうでしょう。医師だったら粛清人事で飛ばされても独立してクリニックの院長となり、むしろ年収が2倍、3倍になるケースは珍しくありません。
ですが会社員には医師免許のようなものはありませんから、大抵は年収ダウン転職を受け入れざるを得ないと思います。50代以上だったらよほど優秀な方でもない限り、転職自体かなり難しい。
シマオ:しかも住宅ローンを抱え、子どもの教育費が掛かるような状態だったら大変なことになりますね……。
佐藤さん:そうなると、職を失い家を失い、下手すると家族すら失ってしまうかもしれません。そうなったら会社を恨みませんか?
シマオ:恨んじゃうでしょうね……!
佐藤さん:それこそ会社の不祥事を週刊誌に売りつけたり、SNSを通じて匿名で執拗に攻撃したり、いまの時代はそれこそ報復の方法もたくさんあります。もっとひどい場合、追いつめられ精神状態が不安定になった人が、敵対派閥に属している社員に対して物理的な報復をしないとも限りません。
シマオ:た、確かに。自分の人生がめちゃくちゃになったら、そういう行動を起こす人がいてもおかしくないかも……。
佐藤さん:だから普通の会社組織では医師の世界のように徹底した勝敗を付けないことが肝要になるわけです。派閥間や部署間でのトラブルやいざこざがあれば、何とか仲裁し解決したほうがいい。互いに妥協点を探り、できるだけ穏便に済ませるようにするのです。
シマオ:なるほど。そうなると、それこそ会社ではしもんさんのような仲裁役、相談役が不可欠と言うことですね?
佐藤さん:はい、とても大事な役割になると思います。できるだけ明らかな敗者、スポイルされる人を出さないことが重要です。
シマオ:ありがとうございます。しもんさん、いかがだったでしょうか? しもんさんの詳しい職場環境は分からないのですが、いずれにしても割り切る部分が必要なようです。ご参考になれば幸いです。
「佐藤優のお悩み哲学相談」、そろそろお別れのお時間です。引き続き読者の皆さんからのお悩みを募集していますので、こちらのページからどしどしお寄せください! 私生活のお悩み、仕事のお悩み、何でも構いません。それではまた!



